「受難の主日」を迎えた9日、教会の暦はキリストの受難を記念する聖週間に入った。教皇ベネディクト16世は、同日午前、バチカンの聖ペトロ広場でミサをとり行なわれた。
「受難の主日」は、復活祭の一週間前の日曜日で、聖週間の第一日目。この日は、過ぎ越しの神秘を完成させるためにイエスがエルサレムに入城したことを記念する。ろばの子に乗ってエルサレムに入られるイエスを、歓呼する群集がその足元に服や木の枝を敷いて迎えたことから、「枝の主日」とも呼ばれる。
また、この日は、各教区で第21回世界青年の日が記念され、バチカンのミサにもローマ教区の若者たちが多数参加した。また、会場には昨年に世界青年の日国際大会が行われたケルン(ドイツ)と、2008年に次回大会が予定されているシドニー(オーストラリア)からの代表の青年たちの姿が見られた。
ミサの前、教皇は聖ペトロ広場のオベリスクの下で、人々が手にする棕櫚(しゅろ)やオリーブの枝を祝別。その後、王であり救い主であるキリストを称える賛歌が歌われる中、教皇と共に、聖職者・修道者・信者の代表たちは、これらの枝を高くかざしながら大聖堂前の祭壇まで行列した。
教皇はミサの説教で、ゼカリア書にある「シオンの娘よ、喜び踊れ。見よ、あなたの王が来る、高ぶることなく、ろばに乗って」(9,9)、「わたしはエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を絶つ。戦の弓は切れ、民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、川から地の果てまで及ぶ」(9,10)という言葉を引用されながら、イエスのエルサレム入城によって完成された預言を、「清貧」「平和」「普遍性」の3つの点から解説された。
そして、貧しい人たちの間にある、貧しい人たちのための王、平和の王としてのイエス、また、地の果てまでおよぶその王国のすべては、十字架の中に集約されていると述べられた教皇は、「十字架は真の生命の木です。命は、それを独り占めにするのではなく、与えることで得られるのです」と、自分自身を与える愛こそ十字架が象徴する真の生き方であると説かれた。
ミサの後半のアンジェラスの祈りの際、教皇の挨拶に続き、ケルンの若者たちによって、世界青年の日の十字架と聖母画がシドニーの若者たちに手渡された。この十字架は1984年の贖いの聖年にヨハネ・パウロ2世から若者たちに託されたもので、これまで青年たちの集いと共に世界各地をめぐってきた。2年後の世界青年の日シドニー大会に向けて、十字架はアフリカやオセアニア地域などをリレーすることになっている。教皇はこの十字架と聖母画が人間と民族間の平和と和解の道具となるよう祈られた。
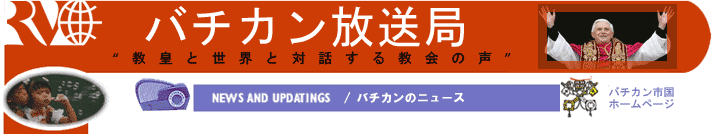
|
|||
|