教皇ベネディクト16世は、使徒的書簡「1970年の改革以前のローマ・ミサ典書の使用についての自発教令」の発布にあたり、世界のすべての司教に宛て、この教令を発するに至った理由およびその根底にある精神を説明する書簡を発表された。
「私は大きな信頼と希望を持ってこの使徒的書簡を司牧者である皆さんの手に託します」と始まるこの書簡で教皇は、今回の教令が長い考察と、様々な協議、そして祈りの結果であることを記しておられる。
教皇は、この教令が発表される以前から現実にはまだ知られざる内容について賛成から反対までかなり異なる反応が見られ、十分な情報に基づかないニュースや判断が少なからぬ混乱を生んだと述べ、この教令をめぐって懸念された2つの問題について直接に説明することを望まれている。
まず、第一に、この教令によって第2バチカン公会議の権威が損なわれるのではないか、特に典礼改革に対する疑問が生じるのではないか、という懸念に対し、教皇はその懸念は根拠のないものであると明言される。
「パウロ6世によって発行され、ヨハネ・パウロ2世によってさらに2回の改訂を経たミサ典書は、当然、ミサの通常形式であり続けます。一方、ヨハネ23世によって発行され、第2バチカン公会議中も使用された公会議前のミサ典書は、ミサ典礼の特別形式として使用されます。ローマ・ミサ典書のこの2つの草稿を2つの典礼であるかのように話すのは適切ではありません。それはむしろ、唯一・同一の典礼を扱っているのです」と教皇はまず注意を促されている。
そして、1962年のミサ典書をミサ典礼の特別形式として使用することにあたり、教皇は、このミサ典書が法的に廃止されたことは決してなく、原則としてそれは常に認可されているものであることを指摘されている。
新しいミサ典書の導入時、前のミサ典書の使用についての規範を出す必要がないように考えられ、起きるかもしれない小さな問題もその時々のケースに合わせて解決されるだろうと想像されていたと、当時を振り返られた教皇は、しかしその後、決して少なくない人々が以前のミサに強く結ばれていることを知ることになったと述べ、その外的なしるしとしてルフェーブル大司教に指導された運動を挙げられた。
多くの人々がはっきりと第2バチカン公会議の拘束的な性格を認め、教皇と司教らへの忠誠を示しながらも、彼らが親しんだ典礼の形式を再び見出すことを望んだ背景には、多くの地域で新しいミサ典書の規定に従わず、これを創造性に対する許可さらには義務のように見なしたことで、忍耐の限界にまで典礼が歪められてしまったことがあったと、教皇は述べられている。
「私は自分の経験から言うのです。なぜなら、私もまた、あの期待と混乱に満ちた時期を過ごしたからです。私は教会の信仰に完全に根ざした人々が、典礼の勝手な歪曲にいかに深く傷ついたかを見たのです」と教皇は記されている。
この問題に対し、ヨハネ・パウロ2世は1988年の自発教令「エクレジア・デイ」をもって、具体的な指示は含まないものの、1962年のミサ典書の使用についての枠組みを示され、これらの信徒に対する司教らの寛大さを呼びかけ、特に聖ピオ10世会との完全なまじわりを再び得るための助けとなることを望まれた経緯を教皇は続いて説明。
残念ながらこの和解は現在のところ実現されていないが、ある共同体はこの教令に示された可能性を喜んで利用したことを教皇は指摘。しかしこのグループの外では1962年のミサ典書の使用は困難なまま残り、そこには、正確な法的規定の不足と、第2バチカン公会議の権威を損ねることになるのではという司教たちの懸念がしばしばあったと述べられている。
これに加え、以前のミサ典書に親しんだ高齢世代以外に、若い人たちの間にもこの典礼形式を見直す傾向が育つにあたり、さらに明確な法的規範の必要性が出てきたと、教皇はこの教令発布の動機を示されている。
また、第2に、1962年のミサ典書の使用の可能性が広がることは、小教区に混乱さらには分裂をもたらすのではないかという懸念に対し、教皇はこの懸念もまた根拠のないものであると述べておられる。
その理由としては、古いミサ典書の使用には、ある一定の典礼的経験とラテン語の知識が前提とされ、それはどちらにしてもそれほど多いものではないからだとされている。したがって、新しいミサ典書がローマ典礼の通常形式として残るのは、法的規範としての理由はもちろん、信徒共同体の現実的側面からも言えることであると指摘しておられる。
教皇はローマ典礼の2つの形式の使用が互いを豊かにし合うものとなるように望まれている。
過去の分裂を越え、真の一致を再び得るまでは、あらゆる努力を惜しんではならないと教皇は強調され、私たちの心を寛大に広げ、信仰が与えてくれるものに心を開こうと、呼びかけておられる。
「2つのミサ典書の間にはいかなる矛盾もありません。典礼の歴史には成長と発展がありますが、一切の分裂はないのです。前世代の人々に聖であったものは、私たちにとっても聖であり偉大であり続けます。それが突然、すべて禁じられ、それどころか害になるということはありえないのです」と教皇は記され、教会の信仰と祈りの中で育まれた豊かさを保存するのは皆のためになることであり、一方で、古いミサ典書に親しむ司祭たちも新しいミサ典書でミサを捧げることを排除することはできないと説かれている。
書簡の最後に教皇は、この新しい規範は司教の権威を決して減ずるものではないと確言されると共に、教令施行から3年後、司教らの経験を教皇庁に報告するよう招かれ、その際、真に重大な困難が現われた場合は、それに対する解決法を見出すであろうと約束されている。
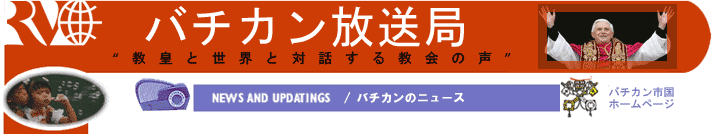
|
|||
|