24日に北イタリアのアウロンツォで行なわれた教皇ベネディクト16世とベッルーノ=フェルトレ教区、トレヴィーゾ教区の司祭たちとの出会いは大変和やかな雰囲気のうちに行なわれ、非常に率直で実りの多いものとなった。
およそ2時間にわたるこの集いでは、両教区を代表する10人の司祭が、日頃司牧の現場から上がってくる問題を教皇に質問し、教皇はこれに対して一つひとつ誠実な回答を示された。
司祭らの質問は、青少年の司牧、司祭職、小教区の仕事、他宗教との対話、離婚者の問題、教区からの宣教師派遣、第2バチカン公会議など、多岐にわたった。
人生の目的や善悪の意識が明確でなく、感覚的に生き、失敗の前に非常にもろい青少年らの司牧に苦心する司祭らに対し、これらの若者たちに「神のいない状態」を見出された教皇は、創造主の存在に気付かせ、その声に耳を傾け、その愛を知らせることで、若者たちは善悪や、命・人生の価値に目覚め、狭い自分から抜け出し神や隣人との生き生きとした開けた関係を築き始めることができると話された。
また、司祭不足などから主任司祭の仕事が増す状況の中で何を優先するべきかという問題に対し、教皇はイエスが72人を任命し派遣した時の言葉(ルカ10,1-2)に「祈り、いやし、告げよ」という司祭職の3つの本質的な役目を指摘され、祈りと聖体、みことばに養われ、自分に託された人々を知り、彼らの魂を秘跡を通していやし、神の国、すなわちイエスにおいて人々の間にある神ご自身を告げることが最も大切であると強調された。
さらに第2バチカン公会議時代を体験した司祭が、公会議の高揚の後で現在抱える一種の「疲労感」を告白すると、教皇は、当時新しい世界、新しい教会を目指して希望に満ちていた公会議時代を振り返り、公会議後の教会の状況が必ずしもすべて理想通りに運ばないとしても、同会議が残した偉大な遺産、その豊かな実りは、教会の歩みの中で決して揺らぐことはないと述べられた。
公会議とは初代教会の教父たちの時代から容易なものではなかったことを教皇は指摘されつつ、長い歴史の中で様々な現実を受け入れ、苦しみと共に成長を遂げてきた教会は、これからも十字架の謙虚さと復活の主の喜びと共に前進していくことができると、力強い励ましを与えられた。
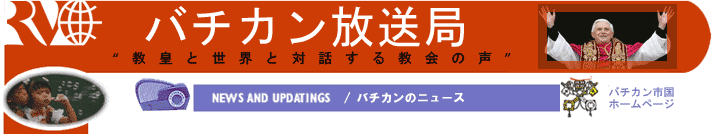
|
|||
|